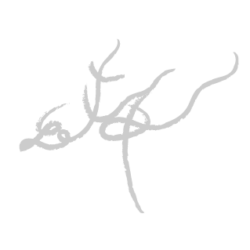踏み締められた歩道の雪は硬く凍っている。
おぼつかない足元に気を取られながら、食事のできる場所を探して歩きまわる。あたりを見渡すと、除雪された雪の大きな山が、青白い街灯に照らされてあちらこちらでぼんやりと光っている。まだ夜も早い時間だが、道沿いの商店はどこもシャッターが降りていて、人通りもない。道路の案内板に添えられた異国の文字に気づき、改めてここが北の果ての街であることを思い出す。時折、スタッドレスタイヤを履いた自動車が、凍った雪を自重で砕きながらゆっくりと通過していく。その大きな音が遠ざかると、自分の靴裏が硬い雪の表面を引っ掻く頼りない音だけが残される。静かな夜。
体が冷え切ったころ、ようやく灯りのついた定食屋を見つける。
雑然とした狭い店内は、夜は居酒屋になるような雰囲気。カウンターに置かれた四角い湯煎鍋にはおでんが煮えていて、その前でビジネススーツの上からコートを羽織った若い女性が食事をとっている。座敷の奥では、仕事終わりらしい男たちが四人、食事を終えて静かに飲みながら談笑している。
手前の座敷に座り、注文をする。奥の男たちは、どこかの現場の職人らしい佇まいだが、年齢も背格好もどことなく揃わない。その違和感になんとなく興味をひかれ、先に出てきたビールを飲みながら、男たちの会話を聞くともなしに聞く。どうやら彼らは、農閑期に出稼ぎにでて、たまたま同じ寮でひと冬を過ごすことになった仲間たちのようだ。お互いの身の上話、家族の話、稼ぎの良い仕事の情報交換。その独特の渇いた距離感に、どこか居心地の良さを感じる。
しばらくして、料理が運ばれてくる。
良く脂の乗った大きなホッケ、小鉢に入った根菜の煮物、溶き卵を落とした味噌汁、柴漬け。腹に温かいものを入れると、ようやく体の芯に残っていた緊張がほどけてくる。奥の男たちの話題は、いつしか同じ寮に、誰かはわからないが、トイレに入る度にトイレットペーパーをひと巻き使い切る奴がいるという話題に変わっている。どんな量の糞をするのだと、冗談を飛ばして笑い合う。思わずその、誰も知らない男の姿をありありと想像する。
黒いシャツを着た神経質そうな兄ちゃんの、どこか粗暴な立居振る舞いと、その癖のように頻繁に前髪に触れる手。廊下ですれ違い、目も合わさずに会釈して足早に立ち去る後ろ姿。
とても食事をしながら聞く話ではないが、その品の無さも含めて、雑にほぐれた空気感と愉快な気持ちが伝播する。味噌汁をかき回すと、出汁に使われた蟹のガラが腕の底をごろごろと転がり、その硬い感触が腕を持つ掌に伝わってくる。そのまま腕に口をつけ、残りの味噌汁を啜る。おいしい。ほんとうにおいしい。
早朝、宿を出て日の出前の街を歩く。
アスファルトの路面も、ブロック塀も、壁も、豪雪地帯特有の痛み方をしている。手をポケットから出して、その冷たくて硬い、街の裸の皮膚に触れてみる。凍結と融解を繰り返す雪に痛めつけられたその荒れた肌に触れていると、この地の長い冬の時間そのものに直接触れているような気持ちになる。
そのままあちらこちらに触れながら港まで歩く。海は穏やかだが、湾口を塞ぐように突き出た埠頭には海流の関係か強い波が打ち寄せており、コンクリートの巨大な防波ドームが頭上を高く覆っている。波の打ち付ける音を、繰り返し低く響かせ続けるドームをくぐり、その先端に出て白み始めた港内を眺める。強烈な寒風。瞬く間に冷えた全身は硬く強ばる。たまらず、来た道を凍えながら引き返す。
浜を歩く。
舟上げ場に置かれた小舟には水が溜まり、中に様々な漁具を浸したまま凍っている。そのつるつるとした氷の表面に触れてみる。そのまま目を上げてあたりを見渡すと、綺麗に形の残った雲丹の殻が、波打ち際に沿ってぽつりぽつりと佇んでいるのが見える。
しゃがみこんで、ひとつひとつ手にとっては眺める。青みがかったベージュ。彼らはそれぞれ、色も大きさも少しずつ異なっている。雲丹は、その無数のトゲの先端に光を感じる細胞があって、いわば全身が目玉であると、どこかで聞いたことを思い出す。
その殻に触れながら、彼らの「見る」を想像する。それはきっと、「触れる」と渾然一体となり、区別されない「見る」なのだろう。彼らがこの冷たい海の底を歩き回り、全身で触れ、全身で見てきたものを、その経験を想像する。見て、歩き、食べ、交配し、その結末として、この美しい殻がここに佇んでいる。そう思うと、上部が円形に開いたその形が、まるで石化した眼球のように、見たということそのものの結晶のように思える。
穴の中を覗き込む。
その何もないようにみえる虚な空間は、きっと彼の「見た」の全てで満たされているのだろう。ずるりと吸い込まれるような、覗き返されたような気持ちになり、思わず目を逸らす。 再びあたりを見渡す。そこには、そんな海の底からまけ出た眼球の化石たちが、波打ち際から冷たく仄暗い故郷を静かに見ている。

岬の北端に向かうバスはガラガラだ。
近くの席では、首から敬老パスを下げたおばあさんが二人、お互いの体にそっと触れながら、仲睦まじく何かを囁き合っている。少し離れた後ろの席では、ジャージ姿の高校生が、大きなスポーツバッグを膝の上で大事そうに抱きかかえて、眠い目をぼんやりと窓の外に向けている。バスは似たような寒々とした小さな漁港の前を、繰り返し何度も通り過ぎてゆく。
しばらくすると高校生はバスを降り、車内には私とおばあさんたちだけが残される。ふたりは変わらず会話に夢中になっているが、エンジンの音にかき消され、その内容は聞き取れない。ぼそぼそとした声の感触だけを耳に感じながら、このふたりはどんな関係なのだろうと想像する。
幼馴染だろうか。姉妹だろうか。同じ時期にこの土地に嫁いできて、同じ苦労を分かち合った友人同士だろうか。バス停で偶々出会っただけの、見ず知らずのふたりだろうか。
当然、ほんとうのことはわからない。しかし、たとえ直接関係を尋ねたとしても、「ほんとうのこと」は、本人たちにも、誰にもわからないのかもしれない。
漁港のひとつでバスは止まり、ふたりはお互いの足元を気遣いながら手を添えて支え合い、ゆっくりとした足取りで降りてゆく。バスが再び動き出すと、車窓からのぞいた寄り添う二つの頭が、漁港と一緒に後方へ流れていく。寂しく一人残された車内から、どこまでも続く灰色の浜を眺める。
岬の停留所でバスを降りる。
あたりを見渡すと、冬枯れの草地に覆われたなだらかな丘陵地帯が広がっている。曇天だが、幸い降り出す気配はない。手前の丘の上には、旧海軍の小さなコンクリート製の望楼が残されていて、遠くに通信用の鉄塔が数本、高く聳え立っているのが見える。そのまま丘を登り、望楼の横を超えて内陸へ向かって歩く。
ゆるやかにカーブを描きながら、登り降りを繰り返す坂道。ふと目をあげると、向こうの丘の稜線から、二羽の猛禽が身じろぎもせずにこちらをじっと見つめている。そのまま立ち止まって、こちらも視線を返す。
彼らの大きな目はきっと遠くまで良く見えることだろう。その目に映る場所のどこにでも、望めばすぐに飛んで行けるのだろう。そんな彼らの目に、この丘は、海は、そして私は、どう映っているのだろう。猛禽の肉体を持って、この風景を見て、その中にいる、というのはどんな感じなのだろう。
稜線の四つの眼球は、静かにこちらを見続けている。その目の奥の、私には知り得ない彼らの世界の中の、私には見ることができない光景の片隅に、いま確実に私の姿がある。その不思議さに、どこか知らない遥か遠くの風に、ふっと撫でられたような気持ちになる。
しばらく丘の上を歩いた後、望楼まで戻る。
その古いコンクリートの構造物は今は展望台になっていて、残念ながら中には入れないが、外側は登ることができるようになっている。壁に手を触れながらゆっくりと階段を登って、岬の風景を眺める。
封じられた建物の窓から中を覗き見ると、そこはがらんどうで何も残されていない。ガラスの向こうに閉じ込められた静止した空気は、ここで経過した長い長い時間を、そのまま保管しているように見える。
その旧い時間の遠い手触りを感じながら、百年前のこの窓の中から、海を監視していた兵士が過ごしただろう時間の断片を想像する。
夜半まで降っていた雪は止み、冷たいコンクリートの望楼の窓からは、静寂の底に沈む岬の風景が、薄明の中に少しずつ浮かび始めるのが見える。丘の向こうの漁村から一筋だけ、ゆっくりと炊事の煙が上がる。夜が明けるにしたがって緊張は少し緩み、そのふと我に帰ったような、しんとした空白に眠気が侵入してくる。軍から支給された外套はゴワゴワと分厚く硬く、湿気を吸って重いだろう。体中にカンテラの油が燃える匂いが染み付いているのを感じるだろう。向こうに見える一筋の煙に、故郷の朝の空気を思い出したかもしれない。
彼の郷里はどこだろうか。雪深い山村の猟師の息子だろうか。田んぼが広がる米どころの、農家の三男坊だろうか。雪など見たこともない南国の漁村の、網元の末っ子だろうか。ひょっとすると、知らぬ間に他国ということになった眼前の海の向こうの島で、獣を狩り野草を採ってくらしていた家族の子なのかもしれない。

岬の先端には、ここが北端の地であることを示す記念碑が、海に背を向けて立っている。
隣接する土産物屋の駐車場には、大きなトラックがぽつんと一台だけ、エンジンをかけたまま止まっている。
駐車場を横切り、記念碑の脇を越えてそのまま波打ち際まで降り、北の果てを望む。
向こうは晴れているのだろう。遠い水平線の上に浮かぶ、豆粒のような異国の山々の頂きは白く光っていて、おもわず手を伸ばして触れたくなる。あちらの海辺にも、南限の汀から同じように異国をまなざす誰かがいるのだろうか。冷たい海は驚くほど凪いでいて、わずかな波の音すら聞こえない。水面はどこまでも平らで、鏡のように鈍色の空を映している。
ふと、あらゆる境界はこのような鏡なのかもしれない、と思う。
まなざし、まなざされ、互いに投影された自身の鏡像に目を凝らす。
そこに映る自身の理解のかたちに、価値の姿に、願望に、憧れに、喜びに、恐れに、憎悪に、怒りに、悲しみに目を凝らす。その像に触れようと手を伸ばしても、指には冷たい水が触れるばかりで、乱れた水面の鏡像はかき消える。決して触れたかった鏡の中のものには触れられない。
なにかを見ようとするということ、見るものと見られるものに分け隔て、輪郭を引くということは、そういうことなのかもしれない。
こちらとあちら、うちとそと。
我が国と彼の国。
社会とわたし、家族とわたし、あなたとわたし。
風とわたし、海とわたし、雪とわたし。
わたしとわたしの肉体、わたしとわたしの心。
わたしとわたしの思い出、わたしとわたしの未来。
わたしを見ているわたしと、わたしに見られているわたし。
そのように、今ここを時間と空間の方向に無数に区切り、幾重にも重ねられた、複雑で精緻な合わせ鏡。
私のちっぽけなからだとその感覚器官で触れられるものは少なく、その小さな知性で知ることができるものは狭く、限られている。私たちは、その合わせ鏡の中に見える、万華鏡のようにどこまでも続く鏡像の広がりによって、世界の広がりを近似しているのかもしれない。
合わせ鏡に閉じ込められた孤独から、その像に触れることを、触れられることを望み、手を伸ばす。
そのように私たちは孤独であり続け、そのように私たちは、想像することしかできない他者に、外部に触れ、確かめ合おうとし続け、手を伸ばし続け、裏切られ続ける。
もし、あの出稼ぎの男たちと、トイレットペーパーを使い過ぎる誰かと、海底をゆっくりと歩く雲丹たちと、二人のおばあさんと、二羽の猛禽と、百年前の兵士と、異国からこちらをまなざす誰かと、話をすることができるのならば、きっと私の貧しい空想は全く裏切られ、未知の万華鏡から見た異質な風光に触れることになるだろう。

バスの時間には未だ数時間の余裕がある。
岬の突端から離れ、海沿いの道を歩く。ゆったりと海に迫り出した、丸みを帯びた丘が重なりあう風景がどこまでも続く。茶色の枯れ草に覆われたその柔らかな丘は、さながら寝そべった巨大な獣の背中のようにも見える。
自分のからだがこのように大きな獣だったとして、海からの風は、打ち寄せる冷たい波は、からだの上に降り積もる雪は、その背の毛並みを食む牛たちの体温は、干し草を運ぶトラックの轍は、リズミカルに歩くヒトの靴裏と体重は、どのように感じられるのだろう。