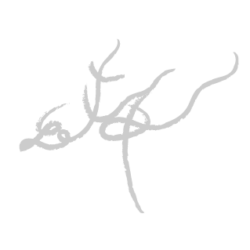晩春、今にも降り出しそうな肌寒い曇天の午後遅く。
駅を出ると人影はまばらで、閑散とした駅前の土産物屋は早々と閉店の準備を始めている。谷あいの古い街道沿いに並ぶ家々の屋根瓦の向こうには、見上げるような山塊が幾重にも重なっている。
土産物屋の店先を覗きながら歩く。いつからあるのかわからない、曇った埃っぽいショーケースの、いつ書かれたのかわからない日焼けした値札の横に、名物らしき餅が裸で並べられているが、薄暗い店先には誰もおらず、奥に見える座敷にも人影はない。半分照明が消された茶店の奥に、学校帰りの子供たちがランドセルをあたりに放り出したまま寝転がって、携帯ゲーム機を覗き込みながら楽しげにふざけ合っているのが見える。数軒並んだ商店や宿屋はすぐに途絶え、そのまま静かな古い町並みが続く。
しばらく行くと、駅名にもなっている古い山寺へ続く参道が左手に現れる。その石畳の道に入り、長い階段を登って大きな山門をくぐる。本堂までは三十分ほどの道程のようだ。ひんやりと湿った針葉樹の巨木の間を縫うようにして、つづら折りの山道を登ってゆく。湿った土と落ち葉の匂い。道は綺麗に整備されていて歩くのに苦労は感じないが、登るにつれて深山の気配は濃厚になってゆく。
道の両脇には、ぽつりぽつりと小さな社やお堂、石塔が祀られている。そのひとつひとつの前に立って、まとっている空気に触れてみる。それらは創建後に少しずつ建てられていったもののようで、中世からごく最近までさまざまな時代のものがあり、それぞれが別の時間の質感と手触りをもっている。
道の終わりは傾斜が厳しくなり、長い石段が続く。目の前を壁のように塞ぐその石段を登り切ると突然視界がひらけ、巨大な本堂が目の前に現れる。中に入ることはできないようだが、白壁の向こうからは人々が立ち働いている微かな気配を感じる。それはこの寺院の日常という時間の手触りで、その感触が改めて現在という時間と、ここがいまも生きている祈りの場であるということを思い出させる。
そのままその伽藍の横を抜け、しばらく細い山道を歩くと、坂の上に灰色の建造物が見えてくる。いかにも古い公共施設といった燻んだ外観で、その巨木の影に隠れるように置かれた鉄筋コンクリートの箱は、山中の風景の中で異質な存在感を放っている。看板を見ると、それは私設の博物館のようだ。

入口でチケットを買い、展示室の中に入る。
一階はこの登ってきた山の自然や成り立ちを紹介する展示がまとめられている。底冷えする薄暗い空間に入るとホルマリンのむせかえるような匂いが充満していて、その匂いが、なぜか山中で感じた土と湿気の匂いを想起させる。室内を見渡すと、岩石、鳥獣や陸貝、昆虫といった生き物、植物などの標本が、スポットライトの丸い光の中に浮かんでいる。
山体を形成する凝灰岩や石灰岩、火成岩などの標本を見る。
その大部分は、赤道付近からプレートに乗って一億数千万年かけてここまで移動してきたものらしい。赤道直下の眩しく光る真っ青な海を想像し、いま立っているこの寒くて薄暗い場所との落差に、目を白黒させる。
壁に並べられた、野鳥や獣たちのパネルを見る。
写真はどれも古い銀塩写真を引き伸ばしたもののようで、ピントも甘く、ぼやけて色褪せている。写されている像の上に積もった、そのシャッターを切った瞬間から経過した時間の堆積が、そこに写る野鳥たちやムササビ、珍しい陸貝を、すべて過ぎ去った遠い昔の誰かの思い出のように見せている。
ひときわ目を引く、部屋の真ん中に積み上げるようにして展示されたきのこの標本を見る。
その保存液に浸され漂白されたきのこたちの、物質としての皮膚が生々しく晒されている姿を見ていると、辱めているような、後ろめたい気持ちになって、思わずそっと目を逸らす。
暗がりに浮かぶひとつひとつの展示物の手触りは硬質で、遠く冷たい。それは、人間にも寺院にも、その祈りにも関心を持たず、粛々と生き死にを繰り返し、物理法則に従ってさまざまな速度で流動する、圧倒的な外部の感触だ。
この部屋に充満する、どこか昏さを感じる匂いは、その流れから切断され、不当に固定された死そのものの匂いなのかもしれない。

二階に上がる。
展示室には、この寺院の寺宝や歴史的遺物がまとめられている。刀剣や書画、古い仏像がずらりと並べられている部屋からは、それらを大切に扱ってきたという手つきそのものの重みを感じる。
千年前の刀剣を見る。
錆に覆われ往時の輝きを失った刀身は、刃こぼれや曲がりなどの戦の記憶をその身に保存している。この刀の柄を握っていたのはどんな手だったのだろう。若侍のほっそりした手だろうか。歴戦の傷だらけの手だろうか。
その手が感じた人を斬る感触を、その手に伝わる、肉体を掻き分けていく背筋が凍るような抵抗を想像する。刀身を刺し込まれた肉体と、その持ち主の最後に見たものを、その場所に渦巻いていた情念の熱量を想像する。
古い祭りの道具や日用品、古釘や建材の一部などを見る。
祭りの準備をした誰かの手、その日用品を丁寧に扱っていた誰かの生活、鍛冶屋の誰かの、大工の誰かの長い修行の時間を想像し、その向こうに広がる世界を手探りする。その感触が、千年以上この山寺に出入りし支えてきた無数の人々がいて、その生活があったという当たり前のことに、少しずつ血肉を与えていく。
そのまま、今から数百年前の、本堂の喧騒を想像する。
蝋燭の光でぼんやりと照らされている、日の入らない建物の奥の暗い廊下。前に立つ男の、産毛の生え始めた月代。隣の若い女性の抱く、ほっぺたを真っ赤にした乳臭い赤子。そのふっくらした小さな手がつかんでいる綿入のほつれた端。その横の中年の男の、白目の濁った鈍い眼差しと、藍染の小袖の襟からのぞく日に焼けて垢じみた硬い肌。向こうに立っている、獣のような虚な目で中空を見つめる老人と、不機嫌そうに彼に話しかけながら手を引く中年の女性。窓の向こう、遠くの明るい参道には、腰に恐ろしい大小を差した侍が数人、神妙な面持ちで床几に腰掛け雑談をしているのが見える。
彼らが普段見ているもの、触れているものを想像する。
冬の朝、水路の冷たい水で大根や菜葉についた土を落とす手触りとその痛み。近所のおかみさんたちの、朝日を透かせた赤い耳と、重なる白い息。振り上げる鍬の、手の脂で黒ずみ、ツヤの出た柄のつるりとした硬さ。夜なべになう草鞋の、束ねた藁を挟み、捻る手のひらの感触。囲炉裏にかざした手の、産毛が焼かれる小さな音と、炭の匂い。目覚めた朝の、暗がりで寝息を立てる家族の体温と、体の下の筵の感触。鋤を引く牛の手綱から伝わる、上気した獣の肉体の呼吸。祭りの時にだけ見られる、並んだのぼりの華やかな色と、遠くから聞こえる笛や太鼓の音。
その彼らの目で、彼らのここでの経験を想像する。
郷の人々や家族に見送られて出立した早朝の冷たい空気。懐に感じる、講仲間から預かった餞別の持ち慣れない重さと、普段の生活から離れた高揚感。一瞬目に入る、飛ぶように追い越していく飛脚の、刺青がびっしりと入った勇壮な後ろ姿。遠くから見た、自分には縁のない大店の軒先に並んだ美しい反物と、そこに出入りする身なりの整った人々。心細さから、子供のように狼や狐狸におびえ歩く夕方の峠道と赤い空。木賃宿で寝入り端にぼんやりと見ていた向こうの戸板。山門前の祭りのような人混みと、物売りの声の賑やかさ。見知らぬ人々とともに登るひんやりと湿った山。唐突に現れ、その大きさに息を呑んだ本堂。畏れのような緊張を感じながら歩く板張りの廊下。暗がりから現れた厳かに歩く僧侶たちの、墨染めの衣と重そうな袈裟。低く唸るような読経の倍音と息遣い。むせかえるような線香の匂いと、目に染みる護摩の煙。蝋燭に照らされ、鈍い光沢を放つ荘厳な内陣の装飾と、その真ん中に立つ仏像。その像に向かって、熱心に手を合わせる周りの人々。
当然、彼らはみな、彼らの生活を各々全うし、遠い昔にこの世から去っている。
みんなどこへ行ってしまったのだろう。
彼らひとりひとりの名前は、親しんだものは、見たものは、感じたことは、望んだことは、愛着のある風景は、くらした世界は、全てきれいに消えてしまったのだろうか。
彼らひとりひとりがそれぞれ大切に抱きかかえていただろう、嬉しかったこと、悲しかったこと、愉快だったこと、辛かったことは、全てなかったことになってしまったのだろうか。
あの硬質な冷たい土と湿気の匂いの、その広い広い向こう側に混ざり、希釈されてしまったのだろうか。

三階に上がると、目の前に畳敷の広間への入口が現れる。
中は三十畳ほどの広さで、壁沿いに仏像が数体、ぐるりと安置されている。そのまま靴を脱ぎ、薄暗い部屋へ入る。くたびれた足には靴を脱いで座れることがありがたい。ここまで登ってくる者は珍しいようで、私以外には誰もいない。隅に積まれた座布団を一つ拝借し、その部屋の真ん中に座る。
少しずつ体の向きを変えながら、周りの仏像を一体ずつ見てゆく。伏目がちで柔らかく立つ姿、憤怒の形相で力強く立つ姿、優美に憂いを含んだ姿、印を結び真っ直ぐに立つ姿。彼らの前に立っただろう無数の人々の後ろ姿を想像する。
閉館の近い館内は、時折どこかの扉を開け閉めする音が遠くから聞こえるほかは、なんの物音もしない。その静けさに、自分が山の中にいるのだということを思い出す。そのままどこを見るともなしに、小一時間ほど、ただ座って過ごす。
この惑星最大の大陸の東端に浮かぶこの群島の上に、この古い都市があり、その北の果ての奥、山の中の、コンクリートの箱の中に、いま自分は座っている。
千年以上前からここには寺院があり、人々に大切にされ続け、その人々は次々と生まれては死に、たくさんの出来事が生起し、去り、その時間の先端にこの薄暗い部屋があって、どういう訳かいま、この地にずっと居た像と同じ場所に、同じ暗がりに一緒に居る。
この仏像を構成する木材には、仏像になる前の樹木として過ごした長い時間があり、壁のコンクリートには、壁になる前の地中で砂礫や鉱石として過ごした長い時間があり、畳のイグサには、畳になる前の露天でのびのびと葉を伸ばした夏の時間があり、そのようにいま目に映るものには、私自身も含めてこうなる前の時間があり、どういう訳かいまここに、それぞれ形をなし、意味と名をおびて一緒に居る。
いつの間にか、ただそのこと自体を噛み締めるような気持ちになる。

目の前に仏像がある。
それは、遥か遠い昔、遥か遠い土地にシッダールタという一人の男が居て、歩いて、話したということが、反響と共鳴を繰り返しながら、遠いこだまをいまのこの場所にまで響かせているという事だろう。 そう考えれば、消えてしまったように見えるあの無数の死者たちの見たもの、感じたもの、くらした世界たちも、巨大な通奏低音のように、いまこの場所で、そのこだまを響かせているのかもしれない。
もしそうだとすれば、きっと、私のいままで見たもの、感じたこと、その全ての瞬間もまた、その巨きな音の中で、そのちいさなちいさな一部として、繰り返しこだまを返しながら、いまここで響き続けているのだろう。