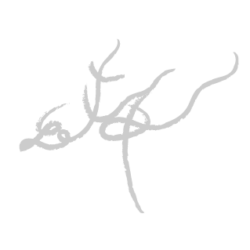夕方の町を歩いている。
都市の外れの山際に残されたその古い住宅地は、柿の木などの植えられた庭のある大きな古い家と、真新しい建売住宅が混在している。狭い路地に入ると、古びた漆喰の塀に残された、いかにも楽しげで伸び伸びとした落書きが目に飛び込んでくる。よく見ると小さく日付が添えられており、どうやら40年ほど前に描かれたもののようだ。
40年前のある日、この壁の前に確かにあった、誰かの楽しい数時間を想像する。彼は、あるいは彼女は、今どこで何をしているのだろう。

春の朝。河口沿いに並ぶ家々の間を縫うように歩いている。
早朝の青い影の中から向こうを見ると、狭い路地の先に明るい空がのぞいているのが見える。そのまま進んで影から出ると、一気に穏やかな河口の風景が広がる。
正面の堤防を見ると、漫画のキャラクターらしきものが描かれていて、それがどういう訳か、この海辺の朝の青い空気にとてもよく馴染んでいるように感じる。虚像である彼だが、ここではちゃんと肉体を持って、ここに居て、歳を重ねて、ちゃんと消えようとしている。

真夏の昼過ぎ。身体中から汗を吹き出しながら、草の生い茂る線路沿いの小道を藪漕ぎのようにして進む。
左手の草むらに立てられたフェンスの向こうには、廃校になった小学校の荒れた校庭が見え、その奥には鬱蒼とした山がのし掛かるように迫っている。そのまましばらく進むと、山側から流れ落ちてきた小川が線路の下に潜りこんでいる場所にぶつかる。そのトンネルは大人がギリギリ屈まずに通れる程度の高さで、一緒に設置された歩道とともに、海側のひらけた場所へ続いている。
かつては通学路だったのだろう。壁面には、この子供には薄暗くて恐ろしいトンネルを、少しでも明るいものにしようとしたような、楽しげな絵が描かれている。

蒸し暑い午後の水田地帯を歩いている。
青々と伸びた稲の根元のぬるい水からは、泥と有機物のむせかえるような匂いが立ち昇ってくる。 畦道を歩いていると、人の気配に驚いた蛙が慌てて飛び込む水音が、あちらこちらから聞こえてくる。舗装道路に出てあたりを見渡すと、向こうに見える用水路のガードレールに、まるでこちらを見る二つの目のような枠があることに気づく。
近づいてしばらく眺める。貼紙かなにかが接着されていたのであろうその糊の跡が、さざ波にゆらぐ水面のように見えてくる。

いまにも降り出しそうな曇天。駅から一直線に伸びる大通りを歩く。
しばらく歩いていると、案の定雨が降り始める。リュックに手を入れ、折り畳み傘を探しながらふと目を上げると、歩道脇の茶色い鉄の箱の表面に、雨粒が次々と鮮やかな線を引いていくのが目に入る。
それは刷毛跡の浮いた平面に、元からあった白い落書きのような線と響き合いながら、一瞬だけ目の覚めるような表情を作り出し、見ている間に塗りつぶされて消える。

あちらこちらを目的も無くうろうろと歩き回る、そんな外れた時間の中に現れる「絵」。それは、見に行こうとしても見られず、偶然出会うことしかできないが、見出そうとすれば無数に見出すこともできる。
誰からも、描き手自身にすら忘れ去られ、見向きもされない。
あるいは、描き手すら存在しない。
それでもそこに在り、その在るということの確かな証拠として、それぞれの肉体に相応しい速度で風化し、その肉体に時を刻みながら、風景の中に、野の中に、あたりまえに、何も言わず静かに去ってゆく。
誰にも見られなかった、選ばれなかった、美しいとされなかった、特別ではなかった、大切にされなかった、愛されなかった、膨大な数の「絵」。そんな無数の、無銘の「絵」が、波しぶきのように水面に現れては消える大海原を夢想する。 この吹き曝しの物理世界の、気が遠くなるほどの広さの中に現れる、肉体としての、あるいは夢としての「絵」。
その野の広大さに触れることで、ようやく息ができるように感じる。