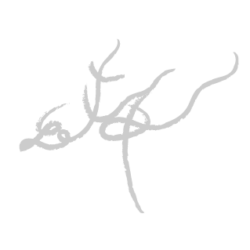秋の初め。なんの脈絡もなく、なにやら大きな、怒りのような悲しみのような強烈な情動に不意におそわれ、眠ることもじっとしていることもできない、そんな夜。
とりあえず体を動かせば落ち着くかと、ひとまず外に出てあてもなく歩く。
住宅街の狭い路地。歩きながら目にうつるブロック塀や電柱に次々と手を伸ばして触れてみるが、あまり感覚は入ってこない。身体の中を渦巻き、出口を求める形のない情動の波に注意力は奪われ、どうしてもまなざしは内向し、いま歩いているはずの夜の光景は半透明な膜の向こうを手掛かりもなく滑ってゆく。喉の奥が閉まり、呼吸が浅くなっているのを感じる。それでも体を動かしていれば多少は楽なようだ。現実感を喪失したまま、しばらく歩き続ける。
いつの間にか雑草の生い茂る川べりの道を歩いている。
足元から伸びる草を軽く掴み、引っ張ってみる。桜の老木の、苔に覆われてゴツゴツとした樹皮を撫でてみる。少し落ち着いたようで、先ほどよりも少し感覚が開いている。草叢に半ば埋まるように設置されているベンチに腰掛け、そのまま寝転がり夜空を見る。頭上を覆う木々の枝の隙間から月が見える。
どのように玄関を出て、どのようにここまで歩いてきたのだろう。思い出そうとしても、他人の記憶を探るような遠い感触で、うまく思い出すことができない。理性ではあまり良い状態ではないことはわかるが、その理性の世界は膜の向こうに見えるばかりで、引き寄せようと手を伸ばしても、ガラスに爪を立てるようになんの手掛かりも無い。
そのまま目を閉じる。一旦運動を止めたせいか、意識の外に追いやられていた周りの音が、堰を切ったように身体に流れ込んでくる。川の流れる音、風の音、遠くの町の喧騒が混ざりあった地鳴りのような音。
起き上がりふと目を上げると、向こうに黒々と鎮座する山並みが見える。
よく知っている山だが、月の光に色彩を奪われたその姿は、かえって尾根筋や樹木の立体感が際立ち、昼間よりもずっと大きく見え、巨大な質量を感じる。
その質量の重力に吸い込まれるようにして、山の姿をじっと見つめる。尾根の一つ一つを、樹木の種類ごとの質感とボリュームの違いを目で撫でるようにして追う。その表面に堆積した、暗く湿った土の層を想像する。その下の、質量の大半を占めるであろう岩塊の大きさを、重さを、手触りを想像する。自分の肉体の体積と質量を、その真っ黒な塊と比べる。
どうしても今すぐにあそこに行かなくてはいけない。
どういう訳か、それが唯一の答えだと確信する。
居ても立ってもいられなくなり、足早に家に帰ると、追われるように準備をして飛び出す。

登山口には未舗装の小さな駐車場があり、奥にはポツンと自動販売機が置かれている。
その灯りの中に自転車を止め、山の中へ向かう坂道を登る。
先ほど遠くから想像していたその黒い塊が、今は視界全てを覆う闇そのもののように目の前に聳え立っている。月は出ているが、森の底にその光は届かない。懐中電灯をつけて、道の先を照らしてみる。小さな光の輪の外は真っ暗だ。その闇は思いのほか不透明で、まるで墨汁の中を泳いでいるように感じる。何度も歩いたことのある道だが、当然ながら昼間とは全く別の世界に変貌している。
あちらこちらから秋の虫の鳴く声が聞こえてくる。
そのままゆっくりと登山道を歩く。家を出る際ついでに手に取ったビデオカメラを取り出し、懐中電灯が照らす先に向ける。
小さな光の輪が、下草の上を滑り、木の根に突き当たり、そのまま幹をなぞるように登っていき、枝の先の葉叢をぼんやり照らすと、中空へとかき消える。斜面を走り、藪を撫で、飛沫を上げる沢の水面に落下し、流れを逆さまに登って、岩の向こうの遠い暗闇に吸い込まれる。
懐中電灯を持つ手を動かして、その光で周囲を触るように確かめる。べっとりと身体に纏わりつく闇の圧力の中で、その小さな灯りが届く場所だけは透明になり、空間が現れる。
樹皮、枯葉、中空に伸びる枝と葉、こんもりとした低木の藪、名前も分からないキノコ、羊歯、柔らかそうな苔類。ダンゴムシ、コオロギ、蝉、ナメクジ、沢蟹。さまざまな形が光の中に現れては消える。漫然と広がっていただけの暗闇が、その具体的な細部の手触りに少しずつ満たされてゆく。背中では、リュックに下げた熊避けの鈴が鳴り続けている。

柳田国男の『山の人生』には、山に駆け入ってしまった者たちの話がいくつも載っている。
世の中への憤懣から遁世した者、産後に発狂した女性、不意にいなくなる娘や子供…。私などはカメラ片手に帰る気満々だが、もっとはっきりと、どうしようもなく、決定的に山に呼ばれ、後戻りのできない形で駆け入ってしまうことも、おそらくはあったのだろう。
濃密な共同体の中で、自身が受け続けている傷に気付くことなく日々を過ごす。傷を対象化する視点も、表現することばも、跳ね除ける力も持てず、ただその渦中で訳もわからずもがき続ける。出口も移動の自由もない世界の中で、その傷の痛みはある日突然、閾値を超える。その圧力は、その力の強さと大きさは、そのどうしようもなさは、いかばかりであっただろうか。
裏を返せばそれは、私たちを強く拘束し、同時に私たちを守ってもいる、群れを形成しようとし続ける運動の、私たちのありようを根底から基礎付け、形作り、それゆえに自明のものとして普段意識することの無い「普通」と呼ばれる信仰の、強さと大きさそのものなのだろう。
かれらは、しばしば人里を懐かしむ。炉の火を、酒を、米の味を恋しがる。しかし、一度出てしまった、追放された群れには、絶対に戻ることができないのだということを、かれらは良く知っている。里の者は、当然の反応として、かれらを尋常ならざるものとして怖れ、群れの外へ、闇の方へと一方的に追いやるだろう。

道から少し外れる。
緩やかな斜面をしばらく登り、そのまま仰向けに寝そべる。腐敗へ向かう枯葉の柔らかな感触と土の匂い。ふくらはぎ、臀部、背中、後頭部の、地面に接触し自重がかかっている箇所から、じわりじわりと湿気が登ってくる。背中側の所々に石や枯れ枝の硬い感触があり居心地が悪いが、どうにも整える気にはなれない。
しばらくそうしていると、湿気と一緒に小さな虫が手足や頭、顔を登ってくる。虫が気持ち悪い、怖いという生理的感覚は、そのまま自身の輪郭の防衛ラインだ。いつもなら当然払い除けるだろうが、起き上がる気にも手足を動かす気にもなれず、少し捨て鉢な、どうにでもしやがれという気持ちでそのまま放置し、懐中電灯を消す。自分の手足も見えぬ闇の中で、体にたかる虫を放置する、という形で後退させた自身の輪郭は、たやすく闇に希釈され混ざり合う。
眼前には不透明な闇があり、まるで埋められているような、息苦しい圧迫感がある。自分は今地面の上にいるのか、土の中にいるのか。そのまま目をつむる。物理的に眼球からの視覚情報を遮断すると、音や気配に対する感度が上がり、周りの大きな広がりが感じられて圧迫感は消える。
頭の近くで小さな虫が歩く微かな音、さまざまな距離から聞こえてくる秋の虫の鳴き声、藪や樹上で何かが動く音。あちらこちらから感じる気配に、都度皮膚が反応してピクリと収縮する。それは自身の不安が投影されたものなのか、本当にそこにあるものなのか。呼吸、心音、汗がにじむ皮膚の感触、土からの湿気。虫の声、夜の鳥の声、遠くの沢の水の音、風が木々を揺らす音。それらの区別は徐々に溶けていき、唯のひろがりそのものになっていく。
知らぬ間に身じろぎでもしたのか、鈴が小さくコロンと鳴り、我に返る。
熊や獣の存在を改めて思い出す。

仏典の捨身飼虎の物語を思い出す。
釈迦の過去生の姿のひとつである、とある国の王子が飢えた虎に我が身を差し出して救う話だが、残念ながら凡夫である私には、虎に喰われるのはさぞ痛かろう、かわいそうで嫌だな、という貧しい感想しかない。
同時に、どこかで読んだ、ライオンに食べられかけ、生還した人のインタビューを思い出す。それは意外にも強烈な多幸感に包まれた体験だったそうだ。脳内麻薬のせいだといってしまえばそれまでだが、もし獣に喰われるという体験がそのようなものであるならば、王子の最後もそんなに悪いものではなかったのかもしれないと、少し気持ちが楽になる。それは生き物にとっては存外幸せな終わりの迎え方なのかもしれない。
とはいえ、当然私はまだ食べられたくは無い。
虫にたかられる程度の刺激からならば後退させることができる私の輪郭も、噛みつかれるような、痛みを伴うような侵襲的刺激にはきっと過敏に反応し、なりふり構わず逃げ出すだろう。
正常な恐怖感が湧き上がりはじめる。無様に抵抗し逃げる自分をありありと想像し、その情けない姿にホッとする。

カメラを起動する。小さな電子音と共に液晶の眩しい画面が点灯し、レンズが微かにジジジと音を立ててピントを探る。
その小さな光と音の向こうにつながる、雑多で断片的な手触りの記憶へのリンクが息を吹き返す。
カメラが売られていた家電量販店の明るい店内と能天気なテーマソング、新品の電化製品から漂う独特の匂い。立ち働く店員たちの顔と垣間見えるバックヤードの空気感。その店のある街角の雑踏の音と匂い。今までそのカメラ越しに見た沢山の光景とその瞬間の心の動き。編集ソフトを操作するカーソルを動かすバーチャルな感触とマウスパッドの上を滑るマウスの重さ、ハードディスクが立てるカリカリという音。
その無数の断片同士のゆるやかなつながりに血が通い始め、自身の生きていた生活空間としてゆっくりと再構成されていく。
はじめてビデオカメラというものを持った日のことを思い出す。
借り物のカメラを恐る恐る構える手のひらに伝わる、テープを回すモーターの感触を思い出す。
ただ映るということが面白かったことを思い出す。
とりあえず撮ってみた、当時住んでいた下宿の板張りの廊下を、急な階段を、共同の台所を、西日の差す明るい玄関を思い出す。
ファインダーの向こうで振り返り、照れくさそうに手を振る友人の、柔らかく油断した中途半端な笑顔を思い出す。
何気なく手に持ったと思い込んでいたカメラだが、そこには帰るつもりがあるということを忘れないための保険のような、命綱に縋るような、思いのほか切実な気持ちが混ざっていたことに気が付く。
立ち上がり、首にかけていたタオルで身体中を払う。

夜の帳は大劇場の緞帳のように重く濃密だ。私たちは透明な街の灯りの中で忘れているが、その帳は、山にも海にも街にも、等しく同じように、はるか昔からずっと変わることなく、繰り返し繰り返し降りてくる。
鈴を手に持ち替えて、コロン、コロンと鳴らしながら闇の中を歩く。
金物が触れ合う音色はこんなにも美しかったのかと、泣きそうな気持ちで聞き入りながら、一歩ずつ山を降りる。鈴がひとつ鳴るたびに、茫洋としていた皮膚感覚にピンと張ったテンションが戻り、それに伴って自身の輪郭が明瞭になってゆく。 いつの間にか、鈴の音に払われるようにしてあの情動の波は遠くに去り、その熱量のなごりだけが体の芯に残っている。